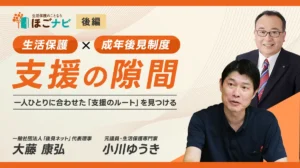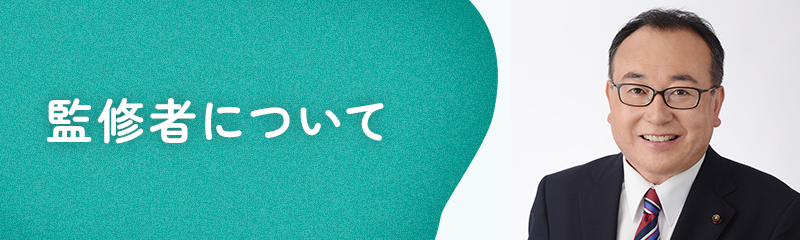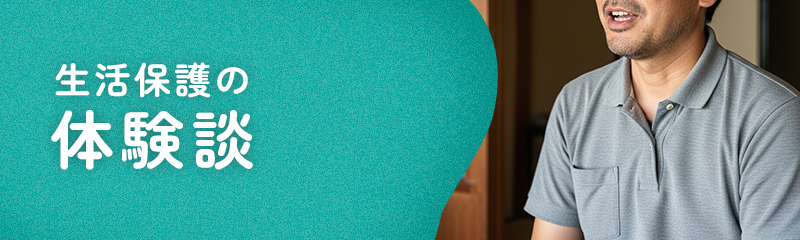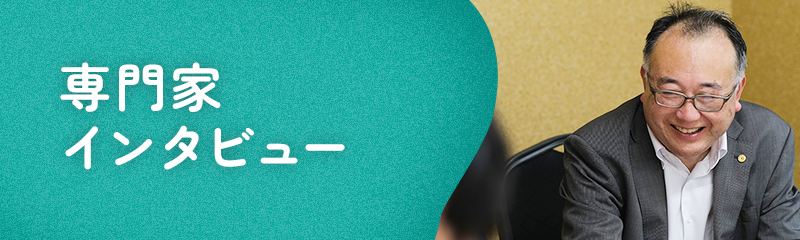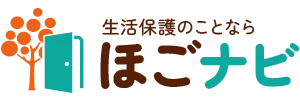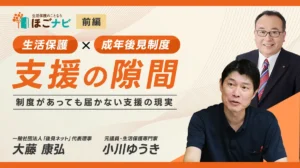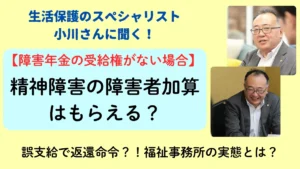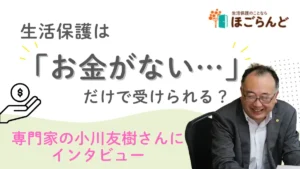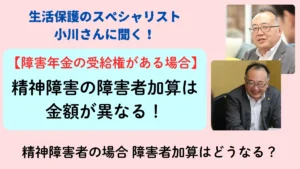【前編】生活保護と成年後見制度の現場から見える「支援の隙間」〜制度があっても届かない支援の現実〜

■大藤 康弘 氏(画像左)
一般社団法人後見ネット 代表理事/大藤社会福祉士事務所 代表
千葉県成田市を拠点に、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)、介護福祉士、ファイナンシャルプランナー等の資格を持つ。成年後見人として多数のケースを担当し、特に生活保護受給者への成年後見制度活用において豊富な経験を持つ。
「制度があっても、本当に必要な人に届いていない」という現場の課題を実感し、一般社団法人後見ネットを設立。財産管理に偏らず、利用者の日常生活全般を支える包括的な支援を目指し実践している。
社会福祉士として培った専門知識を基盤に、利用者一人ひとりが「自分らしい人生を送る」ことを第一に考えた総合的なサポートを提供。法的視点と福祉的視点の両方を持った支援を目指し実践している。
「お金の管理はできるけれど、歯ブラシを買いに行くのは誰が?」「延命治療の判断を迫られても、第三者の私たちには決められない」。成年後見制度と生活保護制度の現場で日々奮闘する専門家たちから聞こえてくる声である。
制度の枠組みはあっても、実際の支援現場では「制度の隙間」で困っている人たちがいる。認知症や障害を抱えながら生活保護を受給する人たちに、本当に必要な支援とは何なのか。弊社が運営する生活保護サポートサービス「ほごらんど」の公式パートナーで、千葉県船橋市役所にて生活保護担当を11年間勤務してきた小川氏と、成年後見人として多くのケースを担当してきた大藤氏に話を聞いた。
(この記事は、2025年7月25日に開催された成年後見制度と生活保護支援に関する対談をもとに構成している)
生活保護と成年後見制度の基本と現実のギャップ

契約はできても「生活」は誰が支える?
「成年後見制度って基本的には金銭管理っていうイメージでいいんですか」という小川氏の問いに、大藤氏はこう答える。
「財産管理、金銭管理というと、契約も含めての財産管理になる。お金の管理とともにお金を取り扱う契約、例えばサービスとの契約をするときにお金が発生するといったものも入っての財産管理という考え方になる」
しかし、生活保護受給者の場合、状況は少し複雑である。大藤氏は具体的な例を挙げて説明する。
「基本的には生活保護でお金を出してもらえるのでお金の面はなんとかなる。でも、施設に入所するとなったとき、入所契約を誰がやりますかとなったら、ケースワーカーさんは厳密にいえばできないので、そこは成年後見人がやります」
ここに現場の実情が現れている。生活保護制度は最低生活費を保障するが、契約行為や手続きの代行はケースワーカーの業務範囲外である。一方で成年後見制度は契約代行ができるが、日常生活の細かな支援は本来の業務ではない。
大藤氏は両制度の連携の必要性をこう語る。
「施設にいる方も含めて、在宅で一時的に入院が必要になったらどうしようとか、お金の部分は生活保護で最低生活を守っていただいている。でも契約の部分に関して、実際の手続きに関してはできないことが多いので、成年後見人である、私が入って、一緒にやるケースはいっぱいあります」
生活保護×後見制度の現場から見るリアル

「親族がいない」「虐待を受けた」人たちの現実
では、どのような人たちが成年後見制度を必要とするのか。大藤氏の経験では、特徴的なケースがある。
「親族がいても意思決定に関して何かしらの障害のある方、虐待ケースですね。虐待があった場合は第三者の後見人をつけて、その方は生活保護で守っていこうという方針になる場合が多い。親族がいない方、虐待ケース、遠方にいて、いろんな事情でお子さんがいても面倒を見てくれない方はいっぱいいらっしゃる」
親族がいても関係が破綻している、虐待を受けた経験がある、遠方にいて支援を受けられない──こうした「身寄りの問題」を抱える人たちにとって、成年後見制度は最後の砦となる。
注目すべきは、高齢者だけでなく若い世代も制度を必要としていることだ。生まれつきの障害を抱えて特別支援学校を卒業したばかりの若者が、生活保護を受けながら一人暮らしをする中で、判断能力の問題から金銭管理ができなくなり、制度の利用を検討するケースも現実に存在している。
銀行でお金が下ろせない日常の困りごと
認知症を発症した人への支援で、大藤氏が重要性を実感するのは日常的な場面である。
「自宅で生活している際に、銀行に行ってお金を下ろせなかったり、カードや通帳を何回もなくしてしまうケースは結構いらっしゃる。そういうことになると、生活に支障が出る」
認知症になっても軽度であれば福祉サービスだけで生活できる人もいるが、金銭管理に支障が出ると途端に生活が成り立たなくなる。大藤氏は以下のように強調する。
「認知症でも問題のない認知症の方もいらっしゃる。福祉サービスのみでやっていける認知症の方もいらっしゃるが、金銭的な問題、経済的な問題が出てきて、本人のお金が全然使えないという状況になったら、成年後見制度がやっぱり必要になってくる」
こうした日常の困りごとから、成年後見制度の申立てに至るケースが多いという。現場では、制度の必要性を痛感する瞬間が頻繁に訪れる。
病院が求める「身元保証人」の現実
入院や施設入所の際に、成年後見人の存在が特に重要になるのが「身元保証」の問題である。
「お金の管理で間に入ってくれる人がいるのであれば、身元保証人、連帯保証人ではないけれども、緊急連絡ができる。身元保証人という難しい概念をわかっている病院はほぼいないのではないか」
大藤氏によると、病院が身元保証人に求めるのは実質的には次のようなことだという。
「緊急連絡先、何かあった時に連絡できる人。亡くなった時とか転院の時に残置物を運んでくれる、本人のご遺体をどうするかという話なので、ケースバイケースですが、成年後見人もできる場合もありますから、それなら身元保証人や連帯保証人がなくても入院させてくださいということになる」
しかし、病院によっては成年後見人がいても受け入れを渋るケースもある。
「中には、身元保証や連帯保証ができない人だと、うちの病院には入院させませんという病院もあるんですね。私も結構困ったことがあった」
こうした実務的な役割を担える人がいることで、病院側も安心して患者を受け入れることができるが、現場では病院ごとの対応の違いが課題となっている。
ケースワーカーとの連携の現実
福祉事務所との関係について、大藤氏は報告業務の実態を説明する。
「行政によって変わってきますが、半年ごとぐらいですかね。収入申告を出してくれって言われたら出すという程度で。出すと言われたら出す、状況に応じてどこまで出すかという感じ。こちらから積極的に出すってことはないですね」
基本的に受動的な報告姿勢だが、チーム支援で重要な役割を果たすはずのケースワーカーとの連携については、大藤氏は率直な現状を語る。
「ケースワーカーさんは人によります。本当に人によって違います」
熱心に取り組む職員もいれば、そうでない場合もある。しかし、ケースワーカーの参加は重要である。
「後見人だけでは何もできないことが分かっているので、ケースワーカーさんにも分かっていただいて」
生活保護費を支給する立場にあるケースワーカーの存在感は大きく、その場にいるだけでも利用者への影響力がある。実際の連携では、ケースワーカーの力量や姿勢によって支援の質が大きく左右されるのが現実だ。
制度の枠を超えた「やりすぎ」な支援
しかし、現場では制度の想定を超えた支援が求められることも多い。大藤氏は率直にこう語る。
「私たちがやってる成年後見人っていうのは、良いか悪いか別として、正直やりすぎな部分もある。法律的な代理人なので、買い物とかも業務ではないし、掃除も受診も一緒に付き合う義務もないし、そんな権限もない」
それでも現実には、誰かがやらなければならない支援がある。
「生活していくと誰かがやらなきゃいけないという部分がいっぱい出てきて、誰かがやらなきゃいけないんだったら私たちがやっぱりやらなきゃいけない。入院の時に物品を揃えるのは誰なのって言われたら誰もいなければ、私たちしかいない。手続きと同時に歯ブラシを買ってきてください、桶を買ってきて、シャンプーを買ってきてって」
このように、制度上は業務範囲外でも、現実的には成年後見人が日用品の購入まで担わざるを得ないケースが頻発している。
「延命治療」の判断という重い課題
制度の限界を最も痛感するのが、医療現場での重要な判断を迫られる場面である。
「病院で、延命しますかとか成年後見人に聞かれることは多いんですけど、それは決められない。私たちは第三者で、認知症になってから出会ったんですからわからないし、命を決めることはできない。でも病院としては聞いてくることは多いです。誰かが決めたいよね。制度的にはそれできないんですけど、お医者さんとか看護師さんとか、聞いてくることが多いですね」
医療従事者は家族のように延命治療について判断を成年後見人に求めてくるが、第三者である成年後見人には決定する権限がない。しかし現実には、誰かが判断しなければならない状況がある。これは、現場としてはわかっているが、制度設計上の大きな課題の一つである。