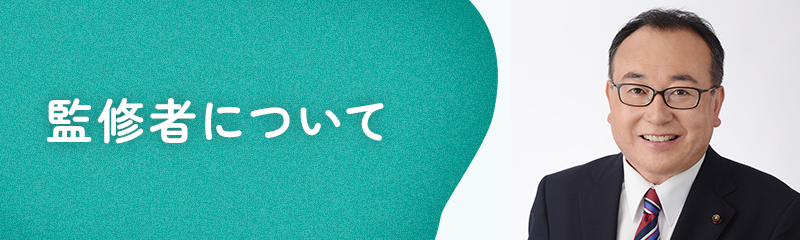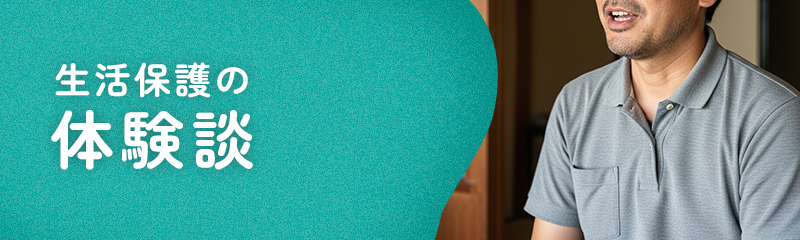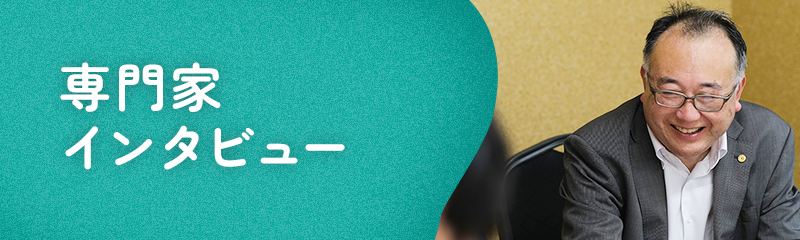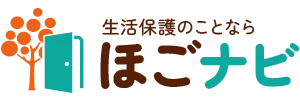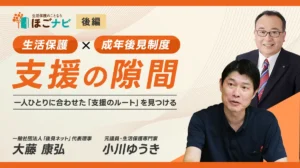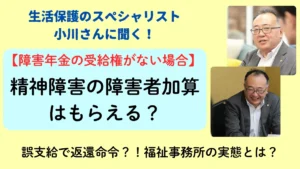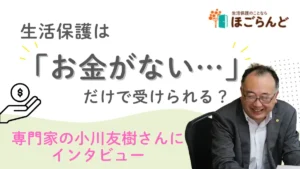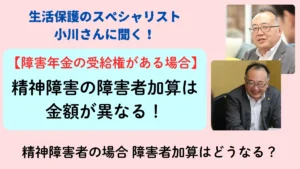【後編】生活保護と成年後見制度の現場から見える「支援の隙間」〜一人ひとりに合わせた「支援のルート」を見つける〜

■大藤 康弘 氏(画像左)
一般社団法人後見ネット 代表理事/大藤社会福祉士事務所 代表
千葉県成田市を拠点に、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)、介護福祉士、ファイナンシャルプランナー等の資格を持つ。成年後見人として多数のケースを担当し、特に生活保護受給者への成年後見制度活用において豊富な経験を持つ。
「制度があっても、本当に必要な人に届いていない」という現場の課題を実感し、一般社団法人後見ネットを設立。財産管理に偏らず、利用者の日常生活全般を支える包括的な支援を目指し実践している。
社会福祉士として培った専門知識を基盤に、利用者一人ひとりが「自分らしい人生を送る」ことを第一に考えた総合的なサポートを提供。法的視点と福祉的視点の両方を持った支援を目指し実践している。
「本人の意思を尊重したいけれど、尊重すると生活が破綻してしまう」「制度の枠を超えた支援が必要だとわかっていても、誰がその責任を負うのか」。支援の最前線で働く専門家たちが日々直面する、答えのないジレンマである。
前編では、成年後見制度と生活保護制度の基本的な仕組みと、現場で起きている具体的な課題を見てきた。しかし、制度の限界を知りながらも、目の前の困っている人を放置するわけにはいかない。現場の支援者たちは、どのようにして制度の隙間を埋め、本当に必要な支援を届けているのだろうか。
後編では、支援者たちの本音と創意工夫、そして制度の改善に向けた提言まで、真に必要な支援の形を探っていく。引き続き、小川氏と大藤氏の対談から、現場の知恵と経験に学びたい。
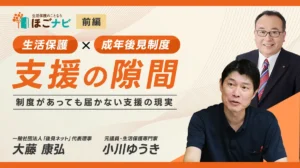
現場が語る支援の本音と課題

「本人の意思尊重」というジレンマ
「まだ元気だから大丈夫」と考える人は多いが、現実はそう単純ではない。小川氏の11年間の生活保護担当経験からも、支援が必要になってから制度を知るケースがほとんどだという。
特に困難なのが、意思決定能力に課題がありながらも強い意思表示をする方への対応だ。大藤氏は実体験を語る。
「認知症ではなくて知的障害などの方だと、あれしたい、これしたいという希望はあるが、その合理性が特にない場合も多い。なんでダメなんだという状況に遭遇したときに、本人の意思を尊重したいと思って尊重したら破綻してしまうこともある」
この現実は、制度利用を検討すべき重要なサインでもある。保護費という限られた予算の中で、本人の意思を尊重しながらも現実的な生活を維持するという、極めて高度なバランス感覚が求められる。
制度への心理的障壁をどう乗り越えるか
「生活保護は恥ずかしい」「後見制度はまだ早い」といった心理的な抵抗感は根強い。大藤氏は、こうした壁を乗り越える秘訣をこう語る。
「コミュニケーションですね。しっかりコミュニケーションをとって、時間をかけてやっていくしかない。王道はないので、この人はこういう特性があるから、こういうルートからアプローチしていこうという形でお話をする」
一人ひとりの状況に応じた個別のアプローチが必要であり、画一的な説明では限界があることを実感として語っている。
身近な人への伝え方
制度について家族や知人に伝える際は、抽象的な説明よりも具体的な実例が効果的だと大藤氏は強調する。
「実際にそういったケースが私どもの相談に来るので、制度を利用した方がいいかどうかお話しさせていただいている」
専門用語や制度の詳細よりも、「銀行でお金が下ろせない」「病院で身元保証人を求められる」といった身近な困りごとから制度の必要性を説明することの有効性を示している。制度の複雑さを理解してもらうより、「いざという時に頼れる仕組みがある」という安心感を伝えることが第一歩となる。
支援のやりがいとこれからの制度

多職種チームによる包括的支援
個人では解決できない複雑な課題に対して、大藤氏はチーム支援の重要性を強調する。
「ドクター、ソーシャルワーカー、看護師、訪問看護師、そしてケースワーカーとの連携が不可欠です。時には本人が信頼する近隣の人の協力も得る」
「この人の言うことだけは聞く。親戚のおばさんや、近隣のこの人だけ聞く、この人の話だけ聞くんだよねみたいな方もいる」
こうした地域の人的ネットワークを活用することで、制度だけでは対応できない支援の隙間を埋めている実情がある。
制度改善への提言
大藤氏は申立て手続きの長期化を大きな課題として挙げる。
「市町村長申し立てはだいぶ時間がかかりますね。半年はかかる、一年以上かかる場合もある。親族調査は各市町村それぞれですし、市町村長申立てが必要な方もたくさんいる自治体も多いので。それが結構大変です」
手続きに時間がかかる間、現場では応急的な対応を迫られ、支援が必要な人への迅速な対応が阻まれている現状がある。
「成年後見の手続きは、まず裁判所に申し立てをするのですが、申し立て権者は、基本的に四親等の親族、本人、市町村長、検察官で、地域包括支援センターや中核機関といわれるところが相談に乗ると思うが、行政によって異なる」
このような複雑で時間のかかる手続きの簡素化が急務である。
現場の創意工夫で支える支援
制度の限界がある中でも、現場の支援者たちは諦めることなく創意工夫で対応を続けている。
「病院によっては、生活保護の方に慣れていることもあり、ケースワーカーとうまく連携してくれるところもある。現実的には困難な対応を求められる病院の方が多いのが実情だが、スムーズに連携してくれるところもある」
完璧な制度はないが、目の前の困っている人を放置するわけにはいかない。大藤氏の言葉からは、制度の枠を超えてでも必要な支援を届けようとする現場の強い意志が感じられる。
現場では、制度活用の判断から手続き支援まで、包括的なサポートが求められている。制度の隙間で困っている人たちを支えるためには、制度の改善と同時に、現場の連携強化と柔軟な支援体制の構築が不可欠である。
そして何より、困っている人を「制度の対象外」として諦めるのではなく、「どうすれば支援できるか」を考え続ける現場の姿勢こそが、真の支援につながっているのである。
大藤氏の最後の言葉が、現場の実情を端的に表している。
「制度ではカバーできないことはあります。そうなんですよ。制度で人間全部見ることなんてできないんです。人間、人生、千差満別です。その辺がやっぱりちょっと制度ではカバーできないなっていう部分です」
制度の限界を認識しながらも、それを乗り越えて支援を続ける現場の専門家たち。彼らの経験と知恵こそが、真に必要な支援の在り方を示しているのである。
支援が必要な人に制度を届けるために
大藤氏が指摘するように、成年後見制度の認知は広がったものの、「制度は知っているが使い方がわからない」「自分には必要ない」と考える人が多い。これは生活保護制度についても同様の課題がある。
特に生活保護については、支援が必要になってから初めて制度を知るケースがほとんどだ。
しかし、「まだ元気だから大丈夫」と考えている間に、銀行でお金が下ろせなくなったり、病院で身元保証人を求められたりと、日常生活で困ることが突然起きる可能性がある。大藤氏が強調するように、「コミュニケーションをとって、時間をかけてやっていくしかない」制度について早めに相談し、理解しておくことが重要なのだ。
そうした課題を受けて、弊社では生活保護申請サービス「ほごらんど」を運営している。経験豊富な専門スタッフが申請手続きから物件居住まで、きめ細かくサポートしている。