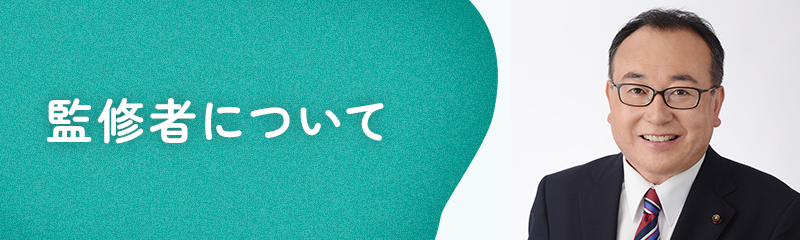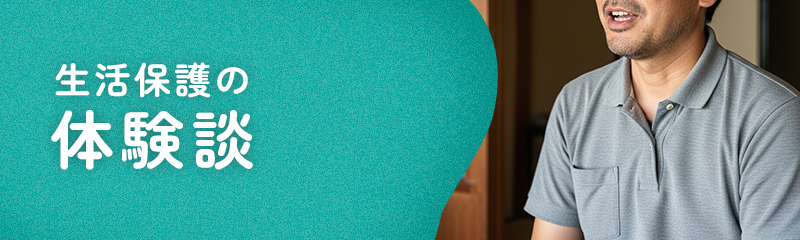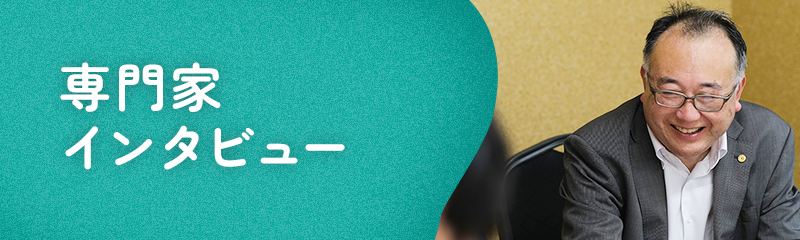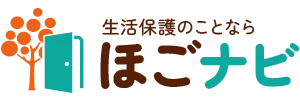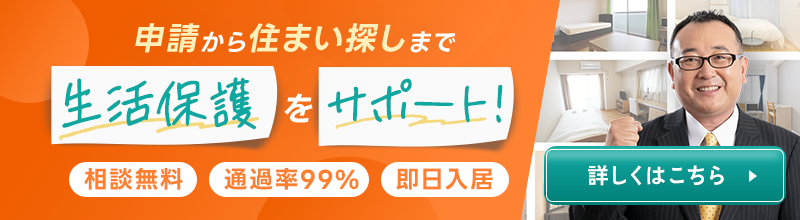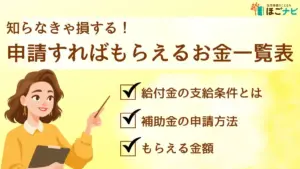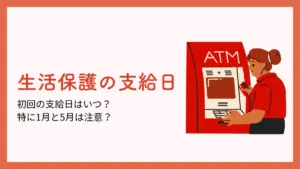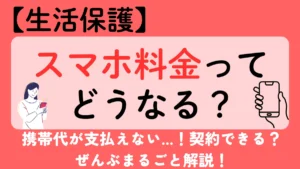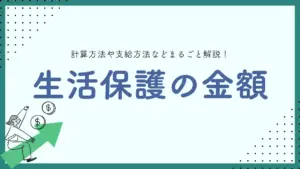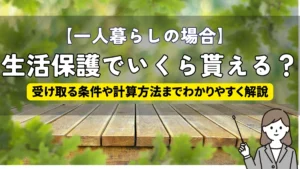申請すると国から貰えるお金・給付金を大解説!一覧表アリ【2025年】

 ほごらんど
ほごらんど実は、申請すれば国から“もらえるお金”がたくさんあるって知っていましたか?
出産や子育て、病気、失業、介護、老後など、人生の節目で必要になるお金は多いものです。幸いなことに、日本には申請すれば受け取れる給付金や補助制度が数多く用意されています。
ただし、こうした支援のほとんどが「自動でもらえるお金」ではありません。
「知らなかった」で損をしないように、あなたやご家族が今すぐ申請できる制度を、この記事でぜひチェックしてみてください。
【この記事でわかること】
- 申請すればもらえるお金一覧表
- 子育て時にもらえるお金
- 高齢者世帯がもらえるお金
- 失業・休業時にもらえるお金
などなど…
- 生活保護ならありとあらゆる支援を受けられる
「受給できるか不安…」という方は、下記ボタンより無料&簡単30秒でできる受給診断をしてみましょう!
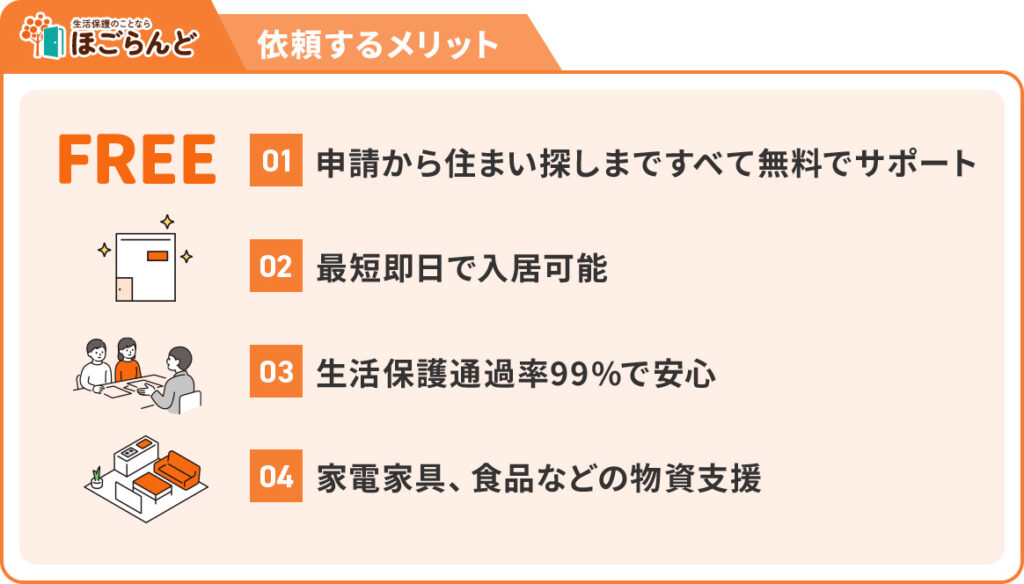
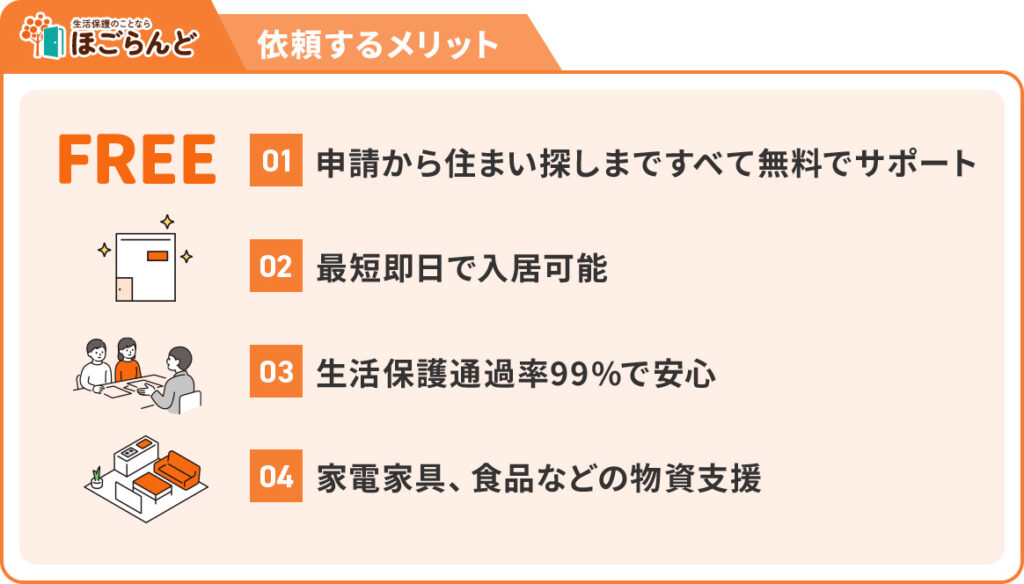
また、下記ボタンより生活保護のスペシャリストにお悩みを無料でご相談いただけます。




知らなきゃ損する!申請すればもらえるお金一覧表



役所がわざわざ言わない、申請したらもらえるお金には一体どんなものがあるのでしょうか。



いい質問ですね。
早速、以下の申請すればもらえるお金一覧表を見てみましょう。
| 申請すればもらえるお金一覧表 | |
|---|---|
| 妊娠出産の際に もらえるお金▽ | 出産手当 |
| 出産育児育児 | |
| 育児休業給付金 | |
| 子育ての際に もらえるお金▽ | 児童手当 |
| 特別児童扶養手当 | |
| 児童扶養手当 | |
| 育児時短就業給付金 | |
| 災害遺児手当 | |
| 就学援助制度 | |
| 資格取得の際に もらえるお金▽ | 一般教育訓練給付金 |
| 特定一般教育訓練給付金 | |
| 専門実践教育訓練給付金 | |
| 高齢者世帯がもらえるお金▽ | 年金生活者支援給付金制度 |
| 高年齢雇用継続給付金 | |
| 高年齢再就職手当 | |
| 失業・休業・休職の際にもらえるお金▽ | 失業手当 |
| 職業訓練受講給付金 | |
| 障害者世帯が もらえるお金▽ | 障害年金 |
| 障害年金生活給付金 | |
| 特別障害者手当、障害児福祉手当 | |
| 介護に関して もらえるお金▽ | 介護手当 |
| 高齢介護サービス費制度 | |
| 居宅介護住宅改修費 | |
| 介護休業給付金 | |
以下では、各補助金(給付金)についてそれぞれ詳しく解説していきます。各項目でもらえる金額や条件なども書いているのでぜひご参考にしてください。
妊娠出産の際にもらえるお金


妊娠や出産は人生の大きなイベントですが、同時に多くの費用がかかります。



病院での検診や出産費用など、経済的な負担を感じる人も多いでしょう。
国や自治体からは、出産や育児を支援するためにさまざまな給付金や補助制度が用意されています。
①出産手当金
会社員や公務員など、健康保険(社会保険)に加入している人が対象となります。
出産手当金の支給条件は以下のとおりです。
【出産手当金の支給条件】
- 勤務先の健康保険に1年以上加入していること
- 出産のために仕事を休んでいる
- 休業中に給与が支払われていない、または減額されていること
- 出産日以前42日(多胎妊娠は98日)〜出産翌日以降56日の範囲で休んでいること
1日あたりの支給額は、以下の計算式で求められます。
1日あたりの金額 = (支給開始前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30) × 2/3
実際の出産日が予定日より遅れた場合、その遅れた日数分も出産手当金の支給対象となります。
②出産育児一時金
健康保険や国民健康保険に加入していれば、勤務形態に関係なく受け取ることができます。支給は通常、病院への「直接支払い制度」を通じて行われます。
支給条件は以下のとおりです。
【出産育児一時金の支給条件】
- 健康保険または国民健康保険に加入していること
- 妊娠4か月(85日)以上で出産した
(流産・死産も含む)
出産育児給付金の支給額については、医療機関が産科医療補償制度に加入しているか否か、また妊娠週数によって異なります。
| 参加医療補助制度 | 妊娠週数 | 支給金額 |
|---|---|---|
| 加入あり | 22週未満 | 一児につき48.8万円 |
| 22週以降 | 一児につき50万円 | |
| 加入なし | 一児につき50万円 |
③育児休業給付金
産後に一定期間、収入が減ることを補うための制度で、男女どちらも対象です。
支給条件は以下のとおりです。
【育児休業給付金の支給条件】
- 雇用保険に加入している
- 育休開始前2年間に11日以上働いた月が12か月以上あること
- 休業中に会社から8割以上の給与を受け取っていないこと
- 1歳未満の子どもを育てていること(最長2歳まで延長可能)
育児休業給付金の支給額は育休開始からの期間によって支給率が変わります。
育児休業給付金には「出生児育児休業給付金」と「一般育児休業給付金」の2つのタイプがあります。
| 出生児育児休業給付金 | 対象者 | 出生後8週間内に産後パパ育休を取得した被保険者 |
| 支給期間 | 出生日から起算して8週間後から6か月後まで | |
| 一般育児休業給付金 | 対象者 | 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した被保険者 |
| 支給期間 | 育児休業期間中 |
子育ての際にもらえるお金





子どもが生まれたあとは、ミルク代や保育料など、生活費の負担が一気に増えます。
申請すれば国からもらえる補助金を正しく理解して申請すれば、年間で数十万円単位の支援を受けられることもあります。
①児童手当
家庭の所得に応じて支給額が変わりますが、ほとんどの世帯が対象となります。
支給条件は以下のとおりです。
【児童手当の支給条件】
- 子どもが日本国内に居住している
- 保護者の所得が所得制限限度額未満であること
児童手当の支給額は、子供の年齢によって異なります。
| 児童の年齢 | 児童手当の額(一人当たり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 (第3子以降30,000円) |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円 (第3子以降30,000円) |
②特別児童扶養手当
身体障害者手帳・療育手帳などの等級によって支給額が決まります。
支給条件は以下のとおりです。
【特別児童扶養手当の支給条件】
- 20歳未満の障がいのある子どもを養育している
- 保護者や子どもが日本国内に居住している
- 所得が一定以下であること
特別児童扶養手当の支給額は、お子様の障がいの区分によって異なります。
| 区分 | 月額支給額 |
|---|---|
| 1級(重度) | 55,350円 |
| 2級(中度) | 36,860円 |
特別児童扶養手当の申請は、居住地の自治体にある窓口でおこないます。
③児童扶養手当
所得に応じて金額が段階的に決まります。
支給条件は以下のとおりです。
【児童扶養手当の支給条件】
- 18歳未満(障がい児は20歳未満)の子どもを養育している
- 父母が離婚・死別・未婚などでひとり親状態である
- 所得が一定以下であること
児童扶養手当の支給額は、お子様の人数によって異なります。
| 子供の人数 | 全額支給の場合(月額) | 一部支給の場合(月額) |
|---|---|---|
| 第1子 | 44,140円 | 10,410~44,130円 |
| 第2子以降 | +10,420円 | +5,210 ~10,410円 |
申請はお住いの地域の市区町村でおこなえます。
④育児時短就業給付
2025年より、雇用保険からの給付として対象が広がっています。
支給条件は以下のとおりです。
【育児時短就業給付の支給条件】
- 雇用保険に加入している
- 子どもが2歳未満であること
- 育休明け後に時短勤務を申請している
- 所得や勤務日数が一定基準内
育児時短就業給付の支給額は休業前の賃金の 10%程度です。事業主の協力が必要なため、勤務先の人事部門に確認が必要です。
⑤災害遺児手当
国や自治体、または日本赤十字社などが窓口となります。
支給条件は以下のとおりです。
【災害遺児手当の支給条件】
- 災害・事故により片親または両親を亡くした18歳未満の子ども
- 国内居住している
- 所得が一定以下であること
災害遺児手当の支給額は児童1人につき月額4,000円です。
小中学校や高校などに入学するとき、または中学校などを卒業後就職するときに支度資金として児童1人につき20,000円が支給されます。
⑥就学援助制度
生活保護世帯またはそれに準じる所得水準の家庭が対象です。
支給条件は以下のとおりです。
【就学援助制度の支給条件】
- 所得が一定以下
- 公立小中学校に通う児童を養育している
所得制限の基準額は以下のとおりです。
| 人数 | 家族構成 | 所得制限 |
|---|---|---|
| 2人 | 父または母、小学生 | 約331万円 |
| 3人 | 父、母、小学生 | 約369万円 |
| 4人 | 父、母、小学生、中学生 | 約432万円 |
| 5人 | 父、母、中学生、小学生、幼稚園 | 約456万円 |
支給額については学年や項目ごとに上限が異なります。詳しくは自治体の公式サイトや福祉事務所までご確認ください。
資格取得の際にもらえるお金


キャリアアップや転職のために資格を取得したいと思っても、受講料や教材費は決して安くありません。
しかし、実は国の就活支援制度を活用すれば、講座費用の一部を国が補助してくれます。
【資格取得の際にもらえるお金一覧】
①一般教育訓練給付金
社会人がスキルアップのために受講する民間スクールや通信講座などに対して、受講費用の一部(上限10万円)が支給される制度です。
最も利用者が多く、パソコン、英会話、簿記などの一般的な講座が対象になります。
支給条件は以下のとおりです。
【一般教育訓練給付金の支給条件】
- 雇用保険に通算3年以上加入している
- 厚生労働省指定の教育訓練講座を受講・修了していること
- 退職後でも、1年以内であれば申請可能
一般教育訓練給付金の支給額は以下のように計算できます。
対象講座の例
・日商簿記検定
・TOEIC講座
・ファイナンシャルプランナー(FP)
・MOS(Microsoft Office Specialist)
・秘書検定 など
②特定一般教育訓練給付金
速やかな再就職や早期のキャリア形成に役立つ講座を受講したい方向けの制度です。
支給率が2倍の40%に引き上げられ、対象講座もより実務的な内容に限定されています。
支給条件は以下のとおりです。
【特定一般教育訓練給付金の支給条件】
- 雇用保険に通算3年以上加入している
- 特定一般教育訓練講座を受講・修了している
- 退職後でも、受講開始日が離職日の翌日から1年以内であれば対象
特定一般教育訓練給付金の支給額は以下のように考えられます。
なお、2024年10月1日以降に受講を開始した方の場合、以下の条件を満たすことで追加の支給が受けられます。
1訓練の修了後に資格取得等をし、修了から1年以内に一般被保険者・高年齢被保険者等として雇用された場合
2雇用されたまま受講した特定一般教育訓練が目標としている資格取得などをした場合
以上の条件を満たしている場合には教育訓練経費の10%に当たる追加支給を受けることができます。
この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の50%(上限25万円)となります。
③専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金は、キャリアチェンジや専門職を目指す人のための最上位制度です。
大学・専門学校・看護学校・ビジネススクールなどの長期講座が対象で、支給率が非常に高く、最長3年間にわたって支援が受けられます。
支給条件は以下のとおりです。
【専門実践教育訓練給付金の支給条件】
- 雇用保険に通算2年以上加入している
(2回目以降の利用は3年以上) - 専門実践教育訓練講座を受講・修了していること
専門実践教育訓練給付金の支給額は以下のように考えられます。
さらに、修了後に就職した場合は追加で20%が支給なので最大で受講費用の70%が支給されます。
高齢者世帯がもらえるお金


高齢になってからの生活では、収入源が年金中心となるため、
「年金だけでは生活が苦しい」「働きたいけれど体力に不安がある」と感じる方も多いでしょう。
そんな中で、国では高齢者の生活や就労を支援する制度が数多く設けられています。
【高齢者世帯がもらえるお金一覧】
①年金生活者支援給付金制度
2019年から始まり、物価上昇への補填としても重要な制度です。
支給条件は以下のとおりです。
【年金生活者支援給付金制度の支給条件】
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 世帯全員の所得が一定基準以下
(単身で年収約88万円以下が目安)
年金生活者支援給付金制度は物価変動に応じて給付額が毎年改定されます。
②高年齢雇用継続給付金
年金との併用も可能で、「定年後の再雇用」で利用する人が多くいます。
支給条件は以下のとおりです。
【高年齢雇用継続給付金の支給条件】
- 雇用保険に5年以上加入している
- 60歳以降も同じ会社や関連会社などで働き続けている
- 60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がっている
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、「60歳になった月から65歳になる月まで」と定められています。
③高年齢再就職手当
再就職したことで残っていた失業給付(基本手当)の一部がまとめて支給される仕組みです。
支給条件は以下のとおりです。
【高年齢再就職手当の支給条件】
- 雇用保険の基本手当の受給資格がある
- 65歳未満で再就職して、1年以上の雇用見込みがある
- 失業給付の残日数が1/3以上ある状態で再就職している
- 離職前より賃金が75%未満になっていないこと
高年齢再就職給付金の支給期間は下記の通り、再就職日の前日時点における基本手当(失業保険)の支給残日数に応じて決まります。
| 200日以上の場合 | 再就職をした日の翌日から2年経過する日が属する月まで |
| 100日以上200日未満の場合 | 再就職をした日の翌日から1年経過する日が属する月まで |
| 100日未満の場合 | 高年齢再就職給付金受給不可 |
失業・休業・休職の際にもらえるお金


仕事を辞めた、または会社の都合で働けなくなったときは、生活費の不安や再就職までのブランクが大きな負担になります。
しかし、国にはそんなときに生活を支えるための雇用保険制度や給付金制度が整っています。
①失業手当
正式名称は「基本手当」で、再就職までの生活を支えるためにハローワークから支給されます。
支給条件は以下のとおりです。
【失業手当の支給条件】
- 雇用保険に1年以上加入していた
- 現在、失業状態にある
- 積極的に再就職を希望している
賃金が高い人ほど低い割合が適用される仕組みです。
②職業訓練受講給付金
「失業手当をもらえない人」や「雇用保険に短期間しか入っていなかった人」でも利用できます。
支給条件は以下のとおりです。
【職業訓練受講給付金の支給条件】
- 職業訓練が必要と認められている
- 所得が低く、世帯全体で一定額以下
- 原則として扶養されていない
職業訓練受講給付金の支給額は以下のとおりです。
| 職業訓練受講給付金 | |
|---|---|
| 職業訓練受講手当 | 月額100,000円 |
| 通所手当 | 月額上限42,500円 |
| 寄宿手当 | 月額10,700円 |
病気やケガが理由で働けなくなった場合は、生活保護の受給をおすすめしています。詳しくは以下のセクションでご覧ください▽
障害者世帯がもらえるお金


障がいのある方やその家族は、医療費や介護費、通院・通学などで日常的な負担が大きくなりがちです。
そうした負担を軽減し、安定した生活を送れるようにするために、国や自治体では年金・手当・給付金など複数の支援制度が設けられています。
【障害者世帯がもらえるお金一覧】
①障害年金
先天的な障がいだけでなく、以下のような病気も対象です。
【対象の病気例】
・うつ病双極性障害
・統合失調症
・発達障害
・がん
・糖尿病
・難病など
年金制度の種類によって「障害基礎年金(国民年金)」と「障害厚生年金(厚生年金)」に分かれ、障害の重さに応じて1級・2級・3級の等級が定められています。



障害年金は、障害者手帳がなくても、また働いていても受給できます。
障害基礎年金
障害基礎年金は、障がい等級によって支給額が異なります。
| 障害等級 | 金額 |
|---|---|
| 1級 | 1,039,625円(月額86,635円)+子の加算 |
| 2級 | 831,700円(月額69,308円)+子の加算 |
また、18歳到達年度末までの生計を維持している子どもがいる場合は、以下の子の加算額が付きます。
| 子供の数 | 金額 |
|---|---|
| 1人目、2人目の子 | 1人につき、239,300円(月額19,942円) |
| 3人目以降の子 | 1人につき、79,800円(月額6,650円) |
障害厚生年金
障害厚生年金(報酬比例の年金)は、人によって金額が違います。「◯級だから◯円」と決まっているわけではありません。
計算方法はとても複雑なので、詳しい金額について以下の記事をご覧ください。日本年金機構-障害厚生年金▷
②障害年金生活者給付金
年金だけでは生活が厳しい人を対象に、2019年から導入されました。
支給条件は以下のとおりです。
【障害年金生活者支援給付金の支給条件】
- 障害基礎年金を受給している(1級または2級)
- 世帯全員の所得が一定基準以下
(単身の場合、年収約88万円未満)
障害年金生活者支援給付金の支給額は、障害基礎年金の等級によって異なります。
| 区分 | 月額支給額 |
|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 6,250円 |
| 障害基礎年金2級 | 5,450円 |
③特別障害者手当、障害児福祉手当
これらは、重度の障がいがあり日常生活で常に介護を必要とする人を養育する家庭に対して支給される手当です。



年金と併用して受け取れる場合もあります。
20歳以上の方を養育する場合は特別障害者手当、20歳未満の場合は障害児福祉手当を受給できます。
(1)特別障害者手当
支給条件
・20歳以上
・重度の障がいがあり、日常生活において常時介護が必要
支給金額
月額:29,590円(非課税)
(2)障害児福祉手当
支給条件
・20歳未満
・重度障害があり、日常生活において常時介護が必要
支給金額
月額:16,100円(非課税)
介護に関してもらえるお金





両親が高齢で、介護が心配です。
国からもらえるお金にはどんなものがあるのでしょうか?



実は、国からの補助金はかなり手厚いです。
介護サービスを受けたときの自己負担を軽減するものから、介護のために休職した人を支援する制度まで、状況に応じたサポートが整っています。
【介護に関してもらえるお金一覧】
①介護手当
全国一律の制度ではなく、各市区町村が独自に設けているため、名称や支給額は地域によって異なります。
支給条件は以下のとおりです。
【介護手当の支給条件】
- 要介護3~5の高齢者を自宅で介護している
- 通算90日以上の入院をしていない
- 世帯が「住民税非課税世帯」である
介護手当の支給額は年間10万円~12万円です。※お住いの自治体によって支給額が異なる場があります。
②高額介護サービス費制度
医療の「高額療養費制度」の介護版と考えるとわかりやすいです。
支給条件は以下のとおりです。
【高額介護サービス費制度の支給条件】
- 介護保険の要介護認定を受けている
- 1か月に支払った介護サービス利用料が自己負担限度額を超えた
なお、月々の負担額上限は、個人の所得や世帯の所得によって決まります。
③居宅介護住宅改修費
手すりの取り付けや段差の解消、浴室の改装などが対象になります。
支給条件は以下のとおりです。
【居宅介護住宅改修費の支給条件】
- 要介護認定を受けている
- 介護保険を利用している
- 改修内容が介護のために必要と認められている
対象となる工事例
対象となる工事例は以下のとおりです。
・手すりの設置
・段差の解消
・滑りにくい床材への変更
・引き戸や洋式トイレへの変更
④介護休業給付金
介護離職を防ぎ、安心して復職できるようにするための雇用保険制度です。
支給条件は以下のとおりです。
【介護休業給付金の支給条件】
- 雇用保険に加入している
- 家族を介護するために休業した
- 介護休業期間中に給与の8割以上が支払われていない
- 介護休業を取得できる期間は通算93日まで
介護休業給付金は休業開始前の賃金の67%支給されます。
【申請すればもらえるお金】生活保護
突然の病気やケガ、うつ病などの精神的な不調によって、働けなくなることは誰にでも起こり得ます。
「もう収入がない」「家賃が払えない」「明日どう生きればいいのか分からない」
そんな不安を抱える人のために、日本には生活を守るための最後のセーフティネットがあります。
それが、「生活保護制度」です。これまで紹介してきた給付金よりも、さらに幅広く生活そのものを支えるのがこの制度です。
生活保護で無料になるもの
生活保護制度とは、病気やケガ、失業などで生活が苦しくなった人に対して、国や自治体が最低限の生活費を支給する制度です。



すべての国民が「健康で文化的な最低限度の生活」を送れるようにするための仕組みです
以下は、生活保護制度で免除になるものや無料になるものです。
| 生活保護で 免除されるもの | 生活保護で 実質無料になるもの |
|---|---|
| 税金 住民税 所得税 固定資産税 軽自動車税 個人事業税 国民年金保険料 NHK受信料 法テラス利用料 | 食費や衣類費、 光熱費などの生活費 家賃や引越し費用 医療費 教育費 介護費 出産費用 自立のためにかかる費用 葬祭費用 |
食費や家賃、教育にかかる費用や医療費まですべて規定の範囲内で無料になります。
生活保護の受給条件
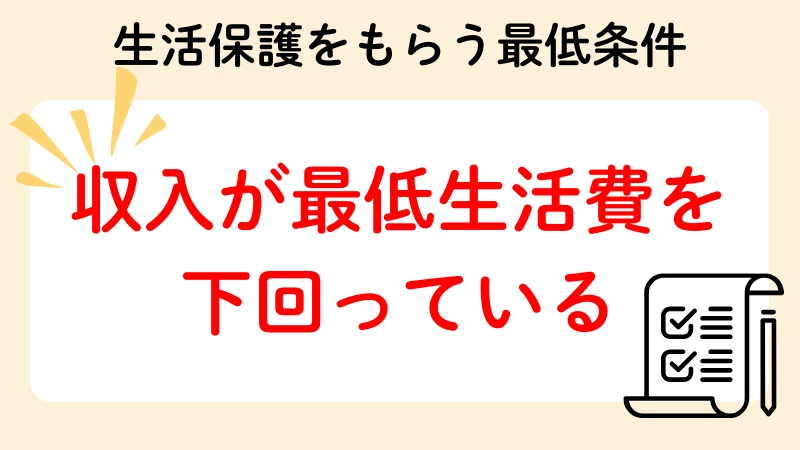
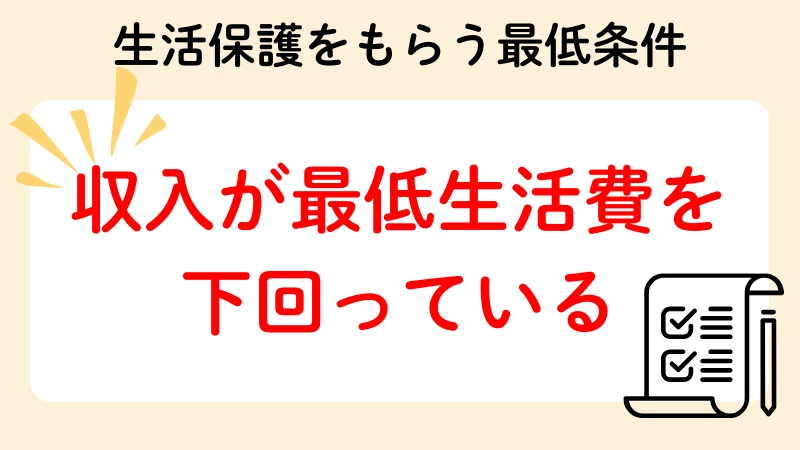
基本的に、「収入が最低生活費を下回っていること」という条件を満たすと生活保護を受給できる可能性が高いです。
最低生活費は、お住まいの地域や世帯人数によって変わります。生活保護の条件について詳しく見る▷
生活保護の支給額の目安
生活保護を受給すると、単身世帯の場合は約13~15万円、母子家庭の場合は約22万円ほど月々に受け取れます。
| ケース | 支給額(目安) |
|---|---|
| 一人暮らし (単身世帯) | 約13万円 |
| 夫婦(二人世帯) | 約18万円 |
| 母子家庭 (子供一人世帯) | 約22万円 |



医療費が無料になる点も大きな特徴です。
生活保護の申請方法
ここでは、生活保護の申請方法を解説していきます。
Step:1 提出書類を準備する


福祉事務所に提出する書類を準備します。
提出書類▽
- 本人確認書類
- 運転免許証、マイナンバーカードなど
- 収入に関する書類
- 給与明細書、年金通知書など
- 住民票の写し
- 保険証の写し
- 預貯金通帳の写し
- 家賃の支払いに関する書類
- 印鑑
書類は、現在の生活状況や経済状況を正確に伝えるために使用されるものです。
不備があると手続きがスムーズに進まない可能性もあります。
ほごらんどでは、無料で書類の作成をお手伝いしています!



面倒な書類の準備もすべてほごらんどにお任せください。
\ 生活支援のプロにお任せ! /
Step2:福祉事務所に申請しに行く


ご自分のお住まいの地域にある福祉事務所の窓口に行って、生活保護を申請したいと伝えます。
しかし、1人で申請しに行っても実は却下される場合も多いです。
Step3:受給に必要な調査を受ける


生活保護が受給できるかどうかの調査が本格的に始まり、以下のことがなされます。
- ケースワーカーからの家庭訪問
- 扶養調査と金融機関への調査
- 申告された収入や資産が正しいか確認する調査
- 他に生活の援助ができる親族がいないか確認
生活保護の審査は、不正受給を防止するために比較的厳しく見られます。
個別の状況によって審査の結果は異なりますが、専門家によるサポートにより、スムーズに申請が進められるケースも多くあります。
Step4:受給開始


生活保護の調査は、申請から14日以内に行われます。遅い場合でも1ヶ月以内には審査結果がわかります。
審査の結果が出て、生活保護を受給できるとみなされたら受給開始です。



ほごらんどは福祉事務所への無料同行サービスや申請書類の作成サポートを行っています。
ほごらんどの生活保護申請サポートを利用する場合の手順
福祉事務所に行く前に、まずはほごらんどに相談することによって、今の自分がいくらもらえるのか、そもそも条件を満たしているのかをお調べできます。
相談は無料です。公式LINEや電話から相談できるので、お気軽にお申し付けください。
\ 生活支援のプロにお任せ! /
ほごらんどのスタッフが、生活保護の申請に必要な書類を丁寧に説明します。
福祉事務所で、ほごらんどのスタッフと同行のもと、生活保護の申請をしに行きます。
お客様一人で申請する場合、実際には受給できる状況なのに「本当に頼れる人はいないのか」「仕事ができるのではないか」といったように厳しく審査されます。
ケースワーカーからの家庭訪問を含め、調査の際には、お客様が希望した場合、ほごらんどのスタッフも同行ができます。
生活保護の申請方法については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
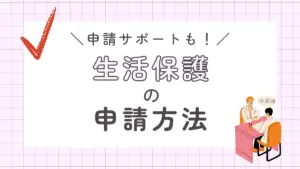
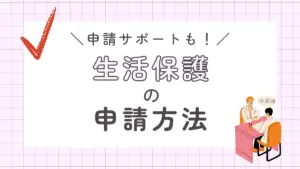
ほごらんどなら申請通過率99%!
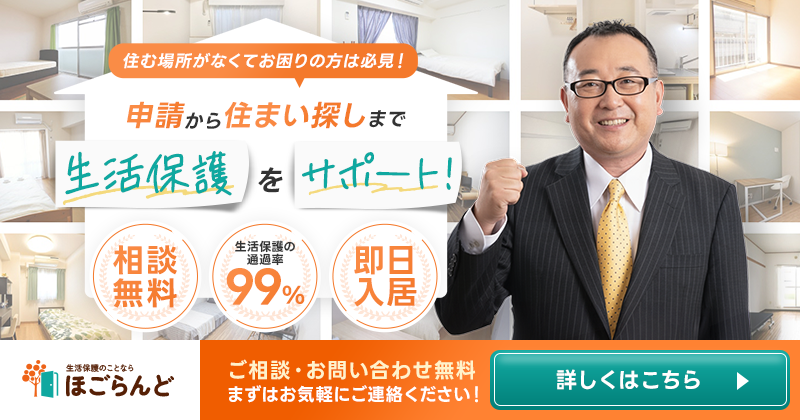
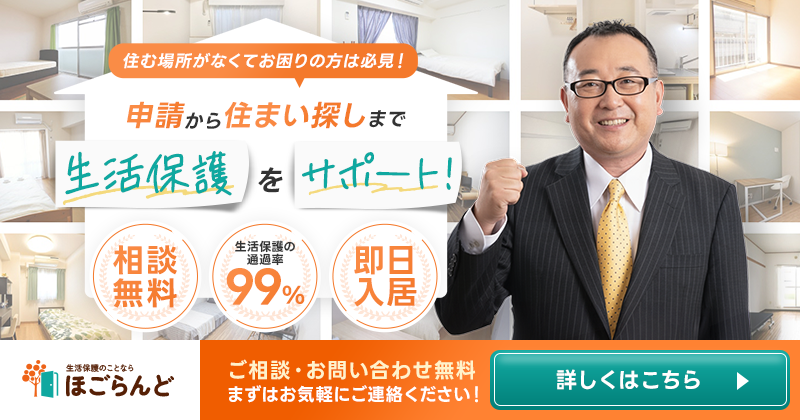
生活保護のことなら、ほごらんどに全てお任せください。
本セクションでは生活保護のメリットを説明した後、ほごらんどの魅力的なサポートサービスを徹底的にご紹介します。
生活保護の大きなメリット
生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。
【生活保護の大きなメリット2選】
- お金の負担が軽減する
- 困窮者の最後のセーフティーネット
メリット① お金の負担が軽減する
生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金の負担が軽減するです。
以下は、生活保護を受けることで支援されるサービスやものの例です。
【生活保護で無料で受け取れるもの】
- 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)
- 家賃、敷金礼金(住宅扶助)
- 基本的なすべての医療費
- 出産費用
- 一定の上限での教育費
このように、要件を満たした場合、最低限度の生活に必要な費用について、制度に基づく支援を受けることができます。



基本的には、生活保護は困窮状態から最低限の生活を取り戻し、自立を目指すための制度です。
メリット② 困窮者の最後のセーフティーネット
二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。
そのため、生活保護脱却後の人生設計のための資格勉強や、自分の人生を見つめ直すための時間が大いにあるのです。
生活保護を受給していたMさんは、生活保護期間中に宅建士の資格を取ることに成功し、今では立派に自立した生活を送っています。



生活保護を受給したことで自分の人生を再スタートさせることができました!
実際にMさんにお話を伺い、その人生大逆転劇を紹介している記事があります。


生活保護は、真に困窮し他に手段がない方のための最後のセーフティネットです。
他にも、以下のような生活保護の体験談を紹介しています。




生活保護のことならほごらんど
生活保護を申請するのは不安で大変なこともありますが、私たちのサービスはその負担を軽減し、スムーズに申請が完了するようサポートします。
個人で生活保護申請を行う場合、手続きの複雑さや必要書類の準備などで困難を感じる方が多くいらっしゃいます。
しかし、生活保護申請サポートサービス「ほごらんど」の担当者が同席した場合の通過率は驚異の99%を実現しており、専門スタッフのサポートによって確実な申請が可能になります。
今家がなくても大丈夫!住居を無償提供&即日入居可
【ほごらんどの住宅サポート内容】
- 敷金・礼金・仲介手数料すべて0円
➡初期費用がなくても大丈夫!! - 最短即日で入居可能!家電・家具付き
➡何も持ってなくても安心して住める - 保証人なしでも入居可能
➡身寄りのない方でも安心!
生活保護申請に伴う住居の手配もお任せください!
受給者様の必要に応じて、快適で生活しやすい住まいを手配いたします。生活に最低限必要となる家具家電もこちらで事前に用意させていただきます。
また、現在家がない状態でも、ほごらんどの提供するお家にすぐに住むことが可能です!
お金がなくても大丈夫!物件から食事までトータルサポート
我々ほごらんどは、受給者様の資産を搾取するようなことは一切致しません。
そのため、生活保護の申請から住居の手配、食事の提供までご希望に沿ってトータルサポートいたします。
何か不安事がある場合のほごらんどへのご相談も無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
【こんな方にオススメ!】
- 面倒で不安な申請手続きを避けたい
- 確実に審査に通過したい
- 安定した住まいと生活環境が欲しい
生活保護が決まった後も、私たちのサポートが続きます。快適な生活環境を提供し、経済的な安定をしっかりサポートします。
電話・公式LINE・WEBサイトで無料相談ができます。今すぐ無料相談をして、生活保護申請の不安を解消しましょう!
ほごらんどなら申請通過率99%!
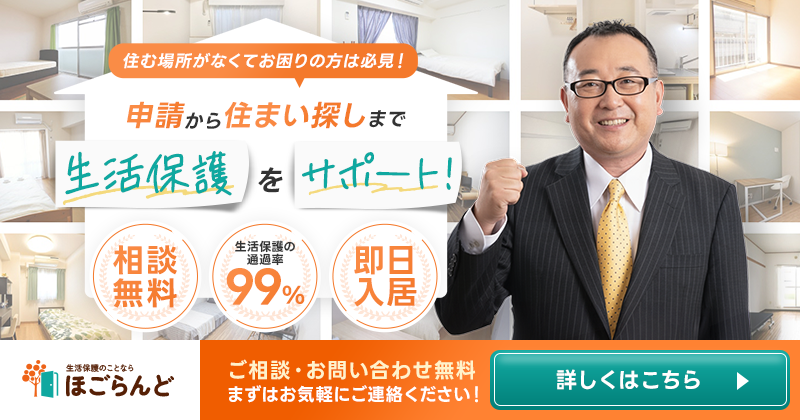
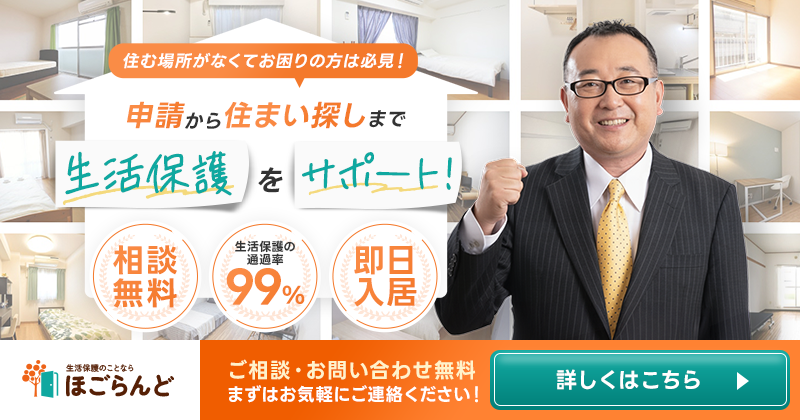
生活保護のことなら、ほごらんどに全てお任せください。
本セクションでは生活保護のメリットを説明した後、ほごらんどの魅力的なサポートサービスを徹底的にご紹介します。
生活保護の大きなメリット
生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。
【生活保護の大きなメリット2選】
- お金の負担が軽減する
- 困窮者の最後のセーフティーネット
メリット① お金の負担が軽減する
生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金の負担が軽減するです。
以下は、生活保護を受けることで支援されるサービスやものの例です。
【生活保護で無料で受け取れるもの】
- 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)
- 家賃、敷金礼金(住宅扶助)
- 基本的なすべての医療費
- 出産費用
- 一定の上限での教育費
このように、要件を満たした場合、最低限度の生活に必要な費用について、制度に基づく支援を受けることができます。



基本的には、生活保護は困窮状態から最低限の生活を取り戻し、自立を目指すための制度です。
メリット② 困窮者の最後のセーフティーネット
二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。
そのため、生活保護脱却後の人生設計のための資格勉強や、自分の人生を見つめ直すための時間が大いにあるのです。
生活保護を受給していたMさんは、生活保護期間中に宅建士の資格を取ることに成功し、今では立派に自立した生活を送っています。



生活保護を受給したことで自分の人生を再スタートさせることができました!
実際にMさんにお話を伺い、その人生大逆転劇を紹介している記事があります。


生活保護は、真に困窮し他に手段がない方のための最後のセーフティネットです。
他にも、以下のような生活保護の体験談を紹介しています。




生活保護のことならほごらんど
生活保護を申請するのは不安で大変なこともありますが、私たちのサービスはその負担を軽減し、スムーズに申請が完了するようサポートします。
個人で生活保護申請を行う場合、手続きの複雑さや必要書類の準備などで困難を感じる方が多くいらっしゃいます。
しかし、生活保護申請サポートサービス「ほごらんど」の担当者が同席した場合の通過率は驚異の99%を実現しており、専門スタッフのサポートによって確実な申請が可能になります。
今家がなくても大丈夫!住居を無償提供&即日入居可
【ほごらんどの住宅サポート内容】
- 敷金・礼金・仲介手数料すべて0円
➡初期費用がなくても大丈夫!! - 最短即日で入居可能!家電・家具付き
➡何も持ってなくても安心して住める - 保証人なしでも入居可能
➡身寄りのない方でも安心!
生活保護申請に伴う住居の手配もお任せください!
受給者様の必要に応じて、快適で生活しやすい住まいを手配いたします。生活に最低限必要となる家具家電もこちらで事前に用意させていただきます。
また、現在家がない状態でも、ほごらんどの提供するお家にすぐに住むことが可能です!
お金がなくても大丈夫!物件から食事までトータルサポート
我々ほごらんどは、受給者様の資産を搾取するようなことは一切致しません。
そのため、生活保護の申請から住居の手配、食事の提供までご希望に沿ってトータルサポートいたします。
何か不安事がある場合のほごらんどへのご相談も無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
【こんな方にオススメ!】
- 面倒で不安な申請手続きを避けたい
- 確実に審査に通過したい
- 安定した住まいと生活環境が欲しい
生活保護が決まった後も、私たちのサポートが続きます。快適な生活環境を提供し、経済的な安定をしっかりサポートします。
電話・公式LINE・WEBサイトで無料相談ができます。今すぐ無料相談をして、生活保護申請の不安を解消しましょう!
申請すればもらえるお金に関するよくある質問
#申請すればもらえるお金#申請すればもらえるお金一覧表#申請すればもらえるお金独身#申請すればもらえるお金2025#国からもらえるお金