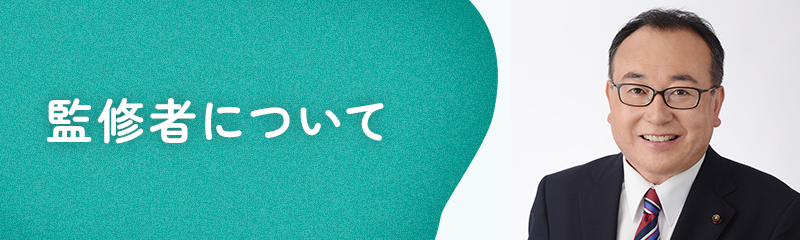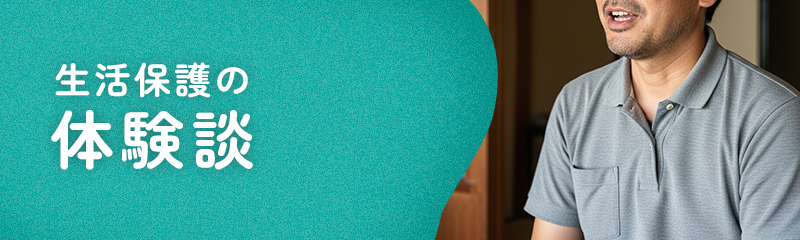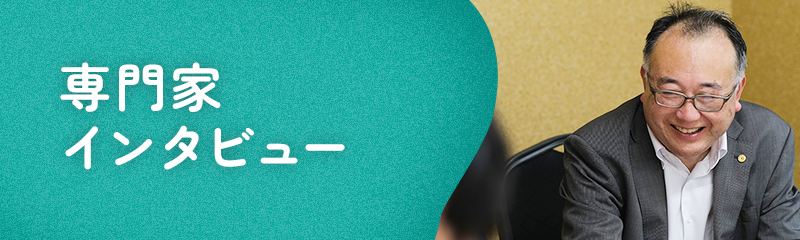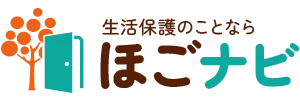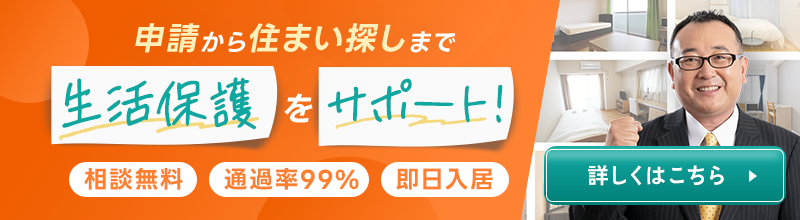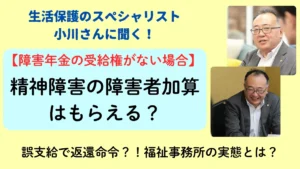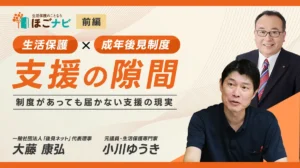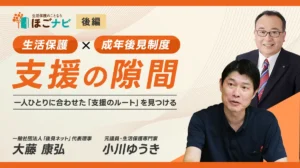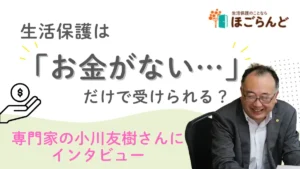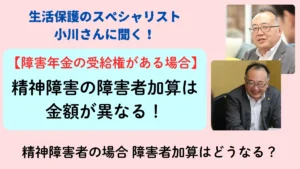【年金受給権がない場合】精神障害の障害者加算について行政書士が解説!
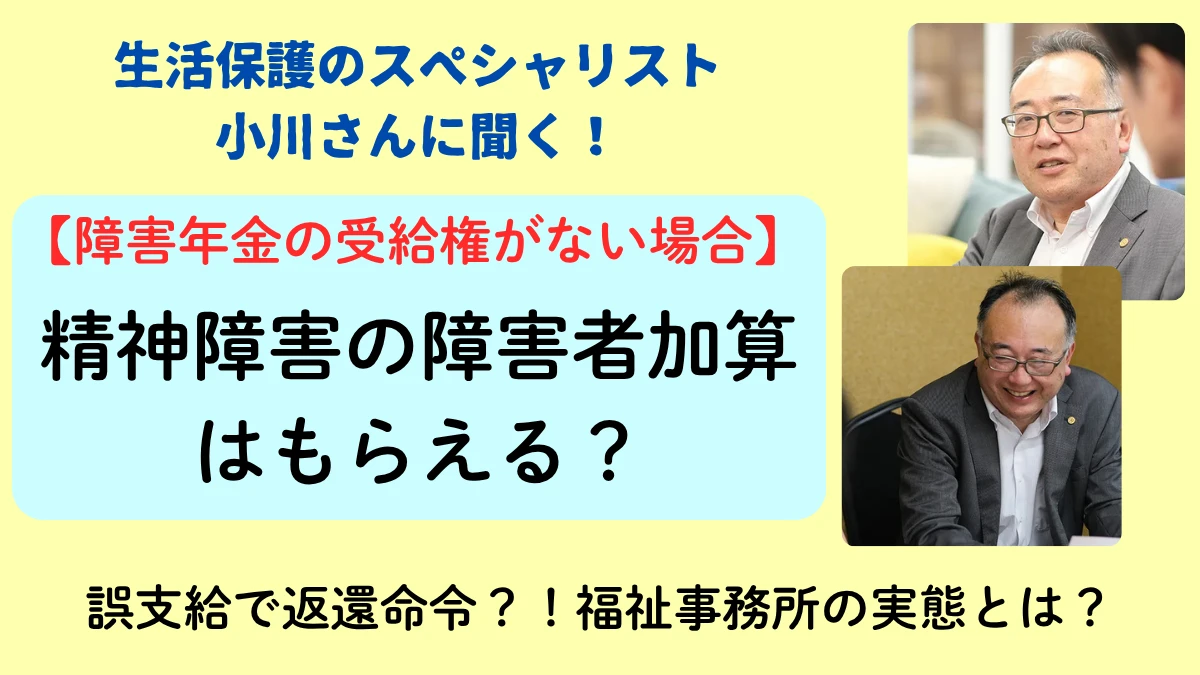
 Aさん(30代)
Aさん(30代)障害年金の受給権がない場合は障害者加算はどうなる?



障害年金の受給権がなくても、障害者加算が認められるケースはありますが、認められないケースも存在し、現場では誤支給や返還トラブルが相次いでいます。
厚生労働省による「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」では、精神障害者手帳の交付数が約120万件に達しており、これは前回の同様の調査(平成28年)のデータから見ると約143%増加しています。
| 令和4年 | 平成28年 | 対前回比 | |
|---|---|---|---|
| 精神障害者保健福祉手帳所持者 | 120.3万人 | 84.1万人 | 143% |
ですが精神障害は、障害年金の受給権がない場合でも加算が認められるケースと、そうでないケースが混在し、現場では誤支給や返還トラブルが後を絶ちません。
一度支給された加算が、後になって「間違いでした」と返還を求められてしまう。その背景には制度の複雑さと、自治体ごとの判断にばらつきがあります。
今回は生活保護制度に長年携わってきた専門家・行政書士の小川友樹さんに、精神障害の障害者加算をめぐる“知らないと損する制度の穴”について伺いました。
登場人物紹介
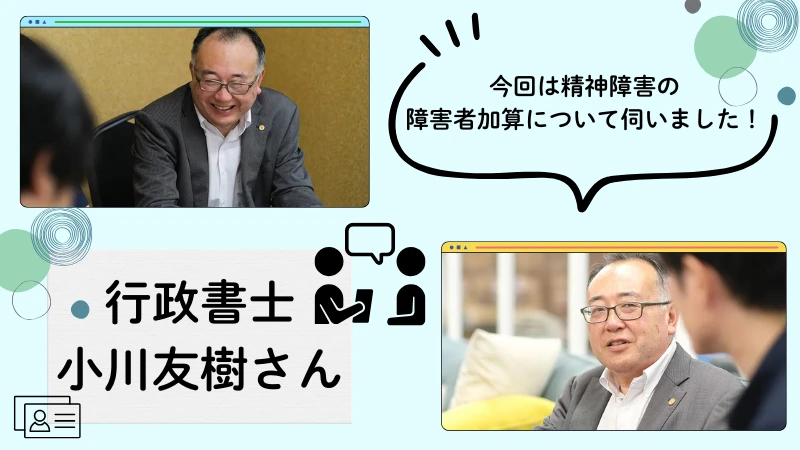
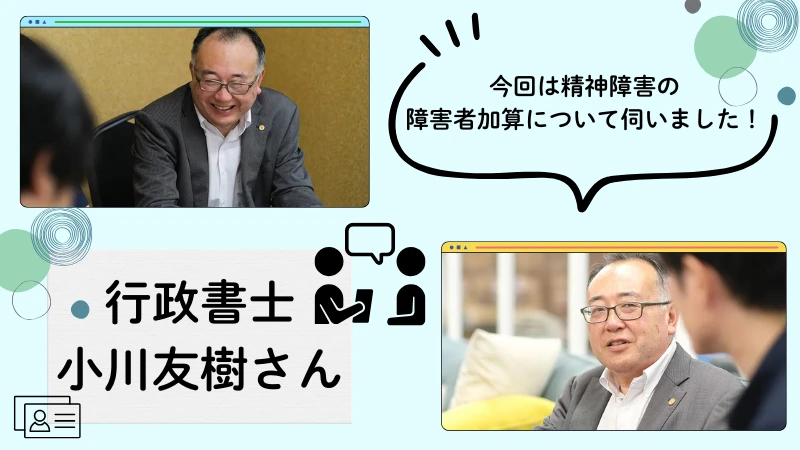
小川友樹(おがわ・ゆうき)さんは、早稲田大学法学部卒業後、千葉県船橋市役所に入庁。21年間の行政キャリアの中で、11年間を生活保護業務に従事。その後は市議会議員として福祉政策を推進し、現在は行政書士として生活保護申請支援に携わっています。
精神障害は加算がつくと思いきや、返還命令される実態
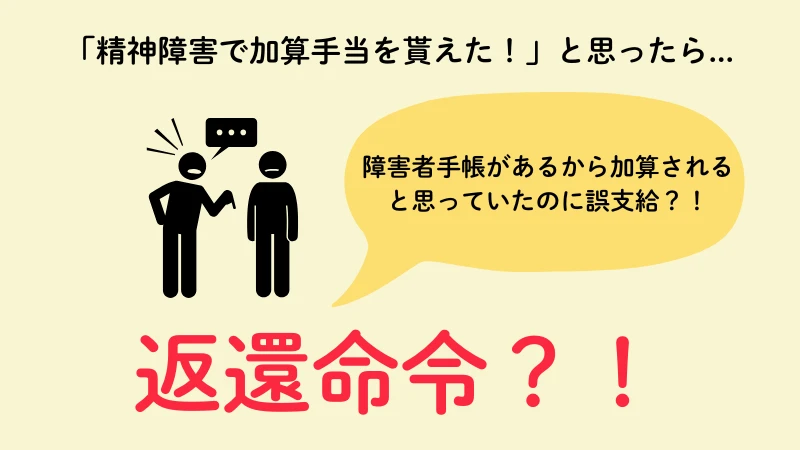
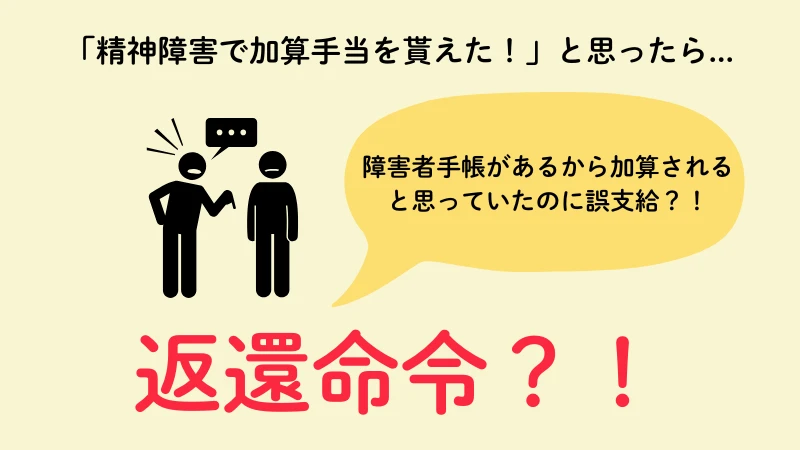
精神障害も対象とされる障害者加算は、
月額で1万〜2万円台にのぼる重要な支援です。
しかし、「障害者手帳がある=加算対象」と思い込むことで、あとから誤支給と判定され、数十万円単位の返還を求められるケースもあります。



精神障害の障害者加算は正しく理解されていないまま支給されていることが少なくありません。
特に『障害年金を受給する権利がない方の場合』の取り扱いは非常に複雑です。
加算の判断基準として多くの自治体が見る項目が、精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の有無。しかし、手帳があるからといって即座に加算対象になるとは限らないのだと小川さんは言います。



初診日(障害認定日)から1年半以上経過していれば、手帳の等級が2級以上で加算対象と判断されるケースも多いです。ただし、そもそも手帳の診断自体が古い場合、現時点の病状と一致していない可能性もある。それを確認しないまま『手帳あるから加算ね』とやってしまうと、後に“誤支給”とされて返還命令が来る。実際に全国でも多額の返還事例が発生しているのです
例え、福祉事務所側の間違えで誤支給⇨返還命令を出されたとしても、受給者は「福祉事務所側の間違えだから返還しなくていい!」というのは通用しません…必ず返還命令に従わなければならないのです。
実際、全国では8000万円規模の返還事例が報告されており、制度を正しく理解しないまま支給を決定することで、利用者・自治体ともに大きなリスクを抱えることになるのです。
受給権がなくても“加算される条件”はある
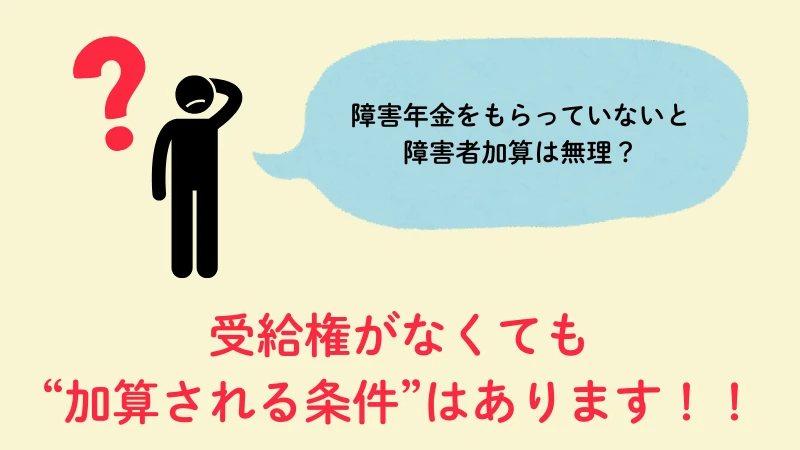
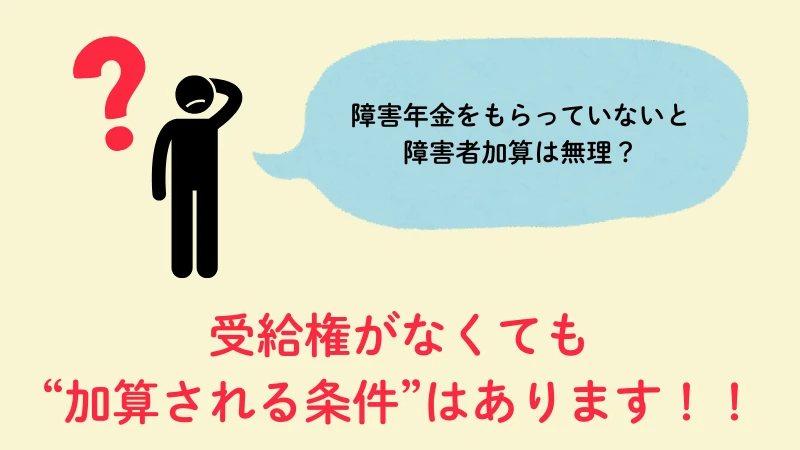



障害年金をもらっていないと、障害者加算は無理?



それは誤解です。
障害年金の“未納”により受給権がない場合でも、手帳の等級や病状によっては障害者加算の対象になる可能性があるのです。
「加算の判断は本来、“障害年金の受給権の有無”とは別の話なんです」と小川さんは続けます。



精神障害で障害年金を受給していない場合でも、“受給権がない=障害年金制度の納付要件を満たしていない”というだけなら、加算は可能な場合があります。



障害年金の納付要件を満たしていなくても、
障害者加算の受給は可能な場合があるんだ!
年金を支払っていなかった人でも手帳の等級や症状によっては障害者加算の対象になりますが、その判断は形式的な確認では不十分です。



例えば2年前に2級で手帳を取得していたとしても、更新の時期に病状が軽くなっていたら、実は3級相当という可能性もある。そのあたりの確認をせずに手帳だけを根拠に加算を認めてしまうと、あとからトラブルになります。そうならないために必要なのは“病状の実態把握”です。
小川さんは、制度の正しい運用には支援者側の知識と注意深さが不可欠だと強調します。
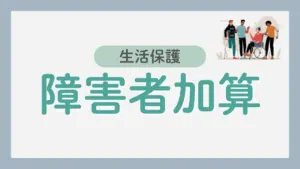
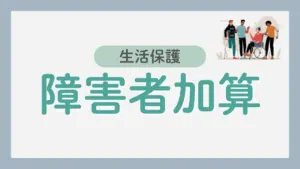
精神障害の加算制度をもっとシンプルにするべき
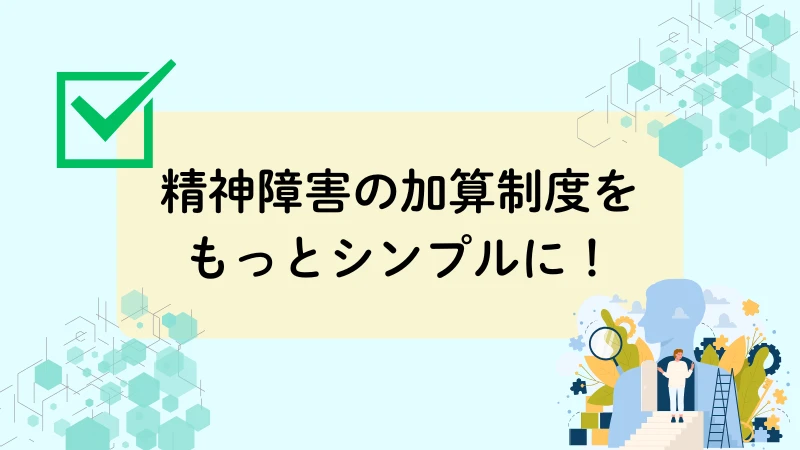
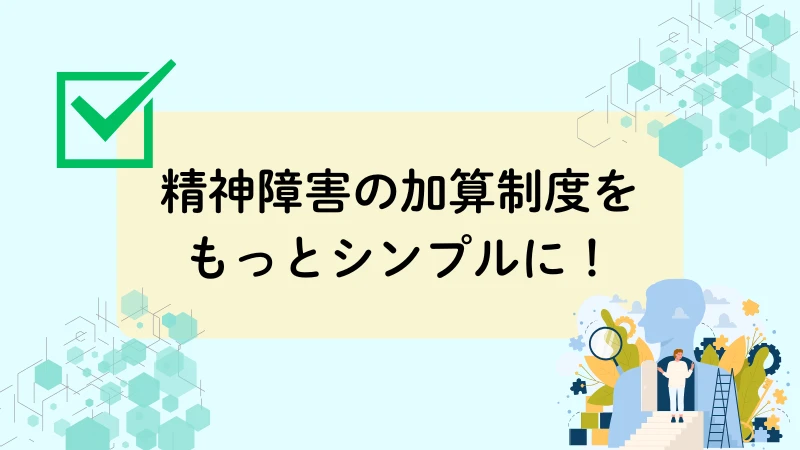
精神障害の障害者加算については、自治体ごとに判断基準が異なるという課題があります。



現場の福祉事務所でも、障害者加算の取り扱いは自治体ごとに大きく異なります。“ある市ではついたけど、引っ越したら外された”なんてことも珍しくない。こうした制度のばらつきは、利用者を混乱させるだけです
小川さんは、精神障害の加算制度を身体障害と同様に、もっとシンプルな仕組みに統一すべきだと提言します。



昔は精神障害というと制度上も扱いが厳しく、手帳保持者も少なかった。ですが、いまや手帳の交付は年々増えており、社会的理解も広まっています。であれば、身体障害と同じように“手帳を持っていれば加算対象”という明快な基準にした方が、運用ミスも減るはずです
さらに、小川さんは精神障害者の支援団体に対してもこう訴えます。



障害者加算は、他の加算が縮小される中でも守られてきた制度です。それだけに、精神障害者団体が声を上げれば制度改正の可能性は十分あると思います。制度がわかりづらくて本来の支援が届かないなんて、本末転倒ですよね
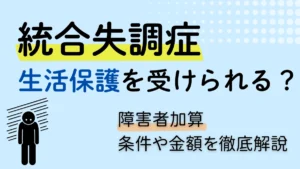
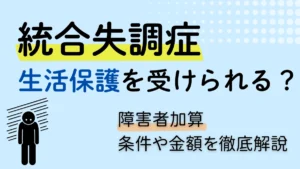
「知らなかった」では済まされない、制度の落とし穴
精神障害の障害者加算は、誤った認識で申請すれば後に“返還”のリスクを伴います。一人ひとりが制度を正しく知り、行政や専門家のサポートを活用することで、はじめて“守られる権利”が実現されるのです。



生活保護は決して恥ずかしい制度ではありません。適切に使えば、人生の再出発を支える大きな支えになります。困っている方は、ぜひ相談してください
現在、小川さんは「生活保護ランド(ほごらんど)」と連携し、情報発信と無料相談支援に注力しています。